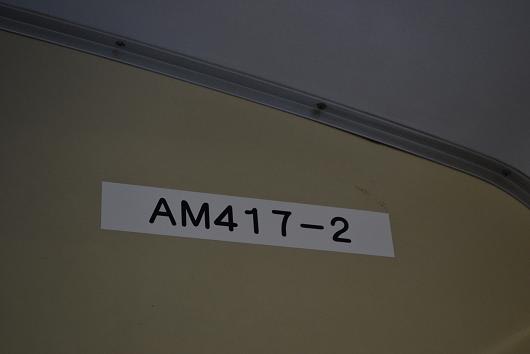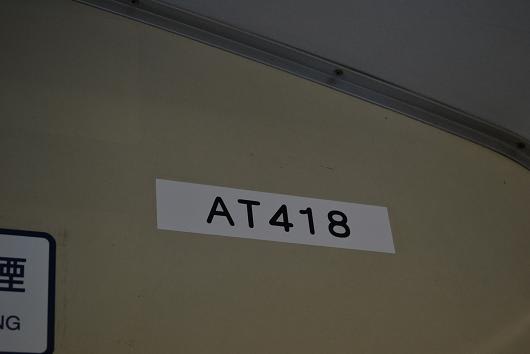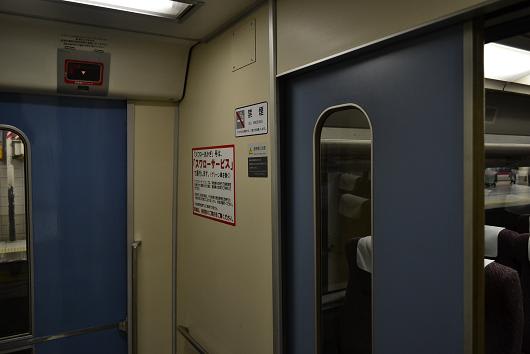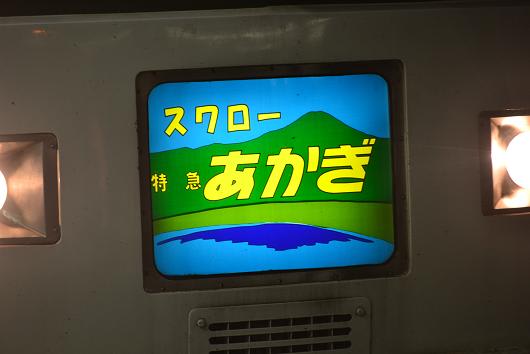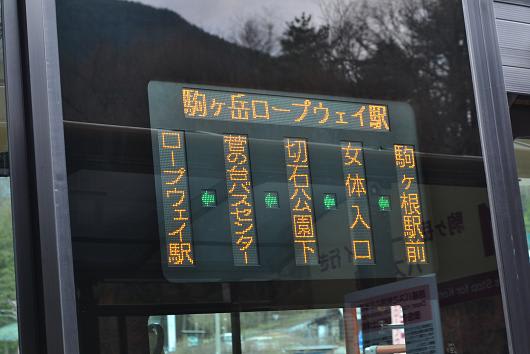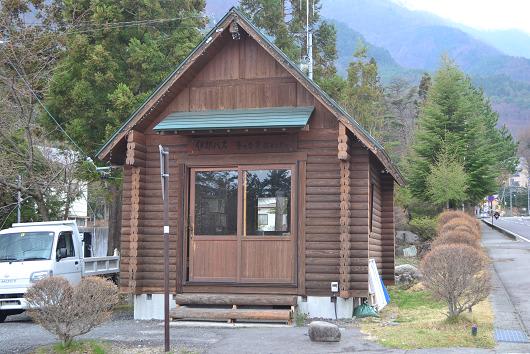仙台のバス見たままです。宮城交通と仙台市交通局で2013年度に新車が入りました。
![]()
![]()
まず、宮城交通からです。宮城交通では毎年数台の新車を入れていますが、2013年度は
大型ノンステ
10台が投入されました。いつもならワンステメインに少数ノンステという感じだったのですが、今回は全てノンステとなりました。10台のうち7台はエアロスターとして投入されています。宮城交通のエアロスターノンステは元サンプルカーや中古車がいますが、新車は今回が初めてとなります。そして、現行ノンステがついに東北でも見られるようになりました。
宮城交通の新車は名鉄グループ共同で購入しているため、基本的に名鉄グループ標準仕様になっていますが、座席カバーなどに違いが見られます。写真は富谷に配置されたM2354です。
![]()
エアロスターノンステは仙台ナンバーもいます。仙台に配置されたS489です。エアロスターノンステは仙台ナンバーと宮城ナンバーの両方ともいるということになります。
![]()
![]()
![]()
エアロスターと同時にいすゞエルガも3台投入されました。エルガの新車が入るのは2008年以来実に5年ぶりとなります。2008年の時はPKG代でしたが、今回はQKG代となっています。エアロスターと同じくATが採用されたようです。ディライトが付いたぐらいで基本的にPKG代とほぼ同じようです(座席カバーも違いますが・・・)。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
仙台市交通局の2013年度新車はこれまでと同じ
エルガ&エルガミオ
として投入されています。これで2009年度から6年連続となりました。でも、ノンステ表記が少し変わったことが相違点です。
![]()
国際姉妹友好都市バスのレンヌ号です。仙台市交通局では国際姉妹友好都市バスを走らせていますが、これまでツーステが担っていましたが、最近になってノンステも担うようになったようです・・・。
![]()
JTBのラッピングとなったエアロスターノンステの607です。宮城交通のラッピングバスは全面が多いだけにJTBのラッピングバスは目立ちますね・・・。
![]()
こちらは仙台駅付近で見かけたタケヤ観光バスのエルガトップドアです。仙台駅から秋保を結ぶ路線バスに充当されているものです。よく見ると、そのエルガは元箱根登山鉄道のようです。側面がキーポイントなのですが、箱根登山鉄道は車両代替のスピードが速く、KL代の廃車が進んでいるようですね・・・。
以上です。


まず、宮城交通からです。宮城交通では毎年数台の新車を入れていますが、2013年度は
大型ノンステ
10台が投入されました。いつもならワンステメインに少数ノンステという感じだったのですが、今回は全てノンステとなりました。10台のうち7台はエアロスターとして投入されています。宮城交通のエアロスターノンステは元サンプルカーや中古車がいますが、新車は今回が初めてとなります。そして、現行ノンステがついに東北でも見られるようになりました。
宮城交通の新車は名鉄グループ共同で購入しているため、基本的に名鉄グループ標準仕様になっていますが、座席カバーなどに違いが見られます。写真は富谷に配置されたM2354です。

エアロスターノンステは仙台ナンバーもいます。仙台に配置されたS489です。エアロスターノンステは仙台ナンバーと宮城ナンバーの両方ともいるということになります。



エアロスターと同時にいすゞエルガも3台投入されました。エルガの新車が入るのは2008年以来実に5年ぶりとなります。2008年の時はPKG代でしたが、今回はQKG代となっています。エアロスターと同じくATが採用されたようです。ディライトが付いたぐらいで基本的にPKG代とほぼ同じようです(座席カバーも違いますが・・・)。







仙台市交通局の2013年度新車はこれまでと同じ
エルガ&エルガミオ
として投入されています。これで2009年度から6年連続となりました。でも、ノンステ表記が少し変わったことが相違点です。

国際姉妹友好都市バスのレンヌ号です。仙台市交通局では国際姉妹友好都市バスを走らせていますが、これまでツーステが担っていましたが、最近になってノンステも担うようになったようです・・・。

JTBのラッピングとなったエアロスターノンステの607です。宮城交通のラッピングバスは全面が多いだけにJTBのラッピングバスは目立ちますね・・・。

こちらは仙台駅付近で見かけたタケヤ観光バスのエルガトップドアです。仙台駅から秋保を結ぶ路線バスに充当されているものです。よく見ると、そのエルガは元箱根登山鉄道のようです。側面がキーポイントなのですが、箱根登山鉄道は車両代替のスピードが速く、KL代の廃車が進んでいるようですね・・・。
以上です。