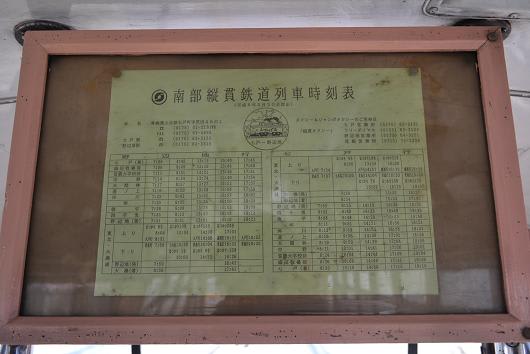帝産バスに元南海バスの
エアロスターノンステ
が投入されました。元南海バスの中古車はエアロスターK、エアロスターM、ニューエアロスター、ブルーリボンなどのツーステを投入してきましたが、ここにきて初めてノンステが投入されました。更に滋賀ナンバーもついに1000台を突破しました。
![]()
![]()
このエアロスターは泉北コミュニティバス用として投入されたもので、泉北コミュニティバスはハイグレード仕様の車両を入れてきているだけにハイグレードな仕様となっていますが、帝産バスに来てもそのままとなっています。ただ、行先表示器は帝産バスが使用している交通電業社製のものに交換されています(まあ、南海バス時代のLED表示器は劣化が進んでいましたからね・・・)。そして、ノンステでありながら一般塗色となっていることがポイントです。でも、前面にはしっかりとノンステップバスと表記されています。そして、帝産バスではノンステに対して車いすマークのシールをリア付近の側面に張り付けていますが、今回の元何回ノンステでも同様に貼りつけられています。
ノンステは山寺に配置され、撮影時はノンステダイヤに入っていました。ノンステダイヤには772が入っていましたが、772が故障がちで代走が頻繁に出ていたそうなので(HPに告知が出されるほど)、バリアフリー化に対する一助になったかと思います。
![]()
ナンバーは滋賀200か1001です。ついに滋賀ナンバーも1000を突破しました。滋賀ナンバーの1000台となると、滋22かナンバー以来となるので、ちょっと懐かしいですね・・・。
![]()
南海バスの泉北コミュニティバス用のエアロスターは2013年にブルーリボン?に代替され、全車廃車になりましたが、昨年には熊野交通と関東鉄道に嫁いでおり、今回で3つめになりますね・・・。しかし、帝産バスでは廃車から1年が経っているのですが、その間どうなったんでしょうか・・・(KC−MP747系は人気あるはずなので・・・)。
![]()
一方、山寺のP代の133はまだ現役で活躍していました。
![]()
そして、近江バスの復刻カラーの6号車もキャッチできました。復刻カラー5台というのは大津3台、あやめ2台という感じなんですね・・・。
以上です。
エアロスターノンステ
が投入されました。元南海バスの中古車はエアロスターK、エアロスターM、ニューエアロスター、ブルーリボンなどのツーステを投入してきましたが、ここにきて初めてノンステが投入されました。更に滋賀ナンバーもついに1000台を突破しました。


このエアロスターは泉北コミュニティバス用として投入されたもので、泉北コミュニティバスはハイグレード仕様の車両を入れてきているだけにハイグレードな仕様となっていますが、帝産バスに来てもそのままとなっています。ただ、行先表示器は帝産バスが使用している交通電業社製のものに交換されています(まあ、南海バス時代のLED表示器は劣化が進んでいましたからね・・・)。そして、ノンステでありながら一般塗色となっていることがポイントです。でも、前面にはしっかりとノンステップバスと表記されています。そして、帝産バスではノンステに対して車いすマークのシールをリア付近の側面に張り付けていますが、今回の元何回ノンステでも同様に貼りつけられています。
ノンステは山寺に配置され、撮影時はノンステダイヤに入っていました。ノンステダイヤには772が入っていましたが、772が故障がちで代走が頻繁に出ていたそうなので(HPに告知が出されるほど)、バリアフリー化に対する一助になったかと思います。

ナンバーは滋賀200か1001です。ついに滋賀ナンバーも1000を突破しました。滋賀ナンバーの1000台となると、滋22かナンバー以来となるので、ちょっと懐かしいですね・・・。

南海バスの泉北コミュニティバス用のエアロスターは2013年にブルーリボン?に代替され、全車廃車になりましたが、昨年には熊野交通と関東鉄道に嫁いでおり、今回で3つめになりますね・・・。しかし、帝産バスでは廃車から1年が経っているのですが、その間どうなったんでしょうか・・・(KC−MP747系は人気あるはずなので・・・)。

一方、山寺のP代の133はまだ現役で活躍していました。

そして、近江バスの復刻カラーの6号車もキャッチできました。復刻カラー5台というのは大津3台、あやめ2台という感じなんですね・・・。
以上です。