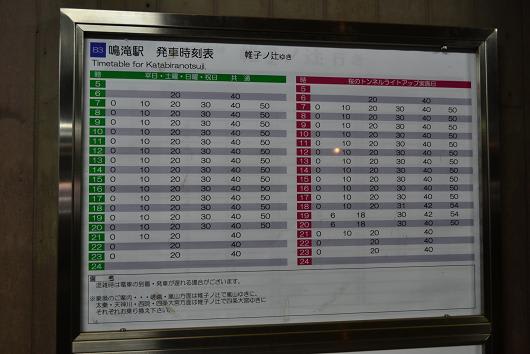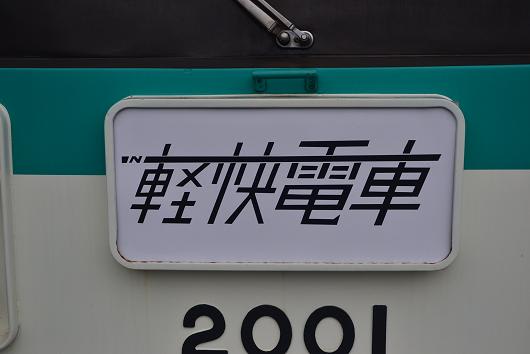旧京都交通は2001年に初のワンステとして
レインボー
を4台投入しました。京都200か 166〜169です。166〜168が亀岡、169が舞鶴に新製配置されましたが、後ほど168が綾部へ転属し、その時点で旧京都交通が会社更生法の手続を行い、南部が京阪バス、北部が日本交通に譲渡されました。そのため、166と167が京阪京都交通、168と169が新京都交通へ引き継がれ、それぞれ離れ離れになってしまいました。
![]()
![]()
京阪京都交通に引き継がれた166と167です。京阪京都交通へ引き継がれた後、2006年に京阪バスカラーへ変更され、更に亀岡から中山(当時)へ転属し、現在に至っています。京阪バスカラーになったとはいえ、違和感なくまとまっています。とはいえ、既に京都交通カラーより京阪バスカラーの方が長くなってしまいました・・・。
![]()
旧京都交通時代の167です。当時は亀岡にいましたが、もっぱら亀岡ローカルで活躍していたため、京都駅に姿を見せる事はほとんど無かったようです(姿を見せていたのは大型車でしたが・・・)。10年前の亀岡駅バス乗り場は比較的狭かったのを思い起こします・・・。
![]()
![]()
京都交通に引き継がれた168と169です。京阪京都交通に引き継がれた車両は京阪バスカラーに変更されたに対し、京都交通に引き継がれた車両は現在も旧京都交通のままで活躍しています。今は廃車が進んで残り少なくなってしまいましたが・・・。168が福知山から舞鶴へ転属し、2台とも舞鶴で活躍しています。幕と社番以外は旧京都交通の面影を残しています。
![]()
旧京都交通時代の169です。169は新製配置時から一貫して舞鶴に配置されている舞鶴生え抜きです。当時も現在と変わらぬ姿で活躍していました。とはいえ、舞鶴管内では路線の再編成と廃止が進み、昔の面影も少なくなっています・・・。
運命とはいえ、同一事業者が投入した車両が会社更生法の適用に伴って別々の事業者へ別れてしまい、それぞれ別の姿になってしまいました。でも、それぞれ使命を背負って活躍していたのが印象的でした。
旧京都交通が無くなって今年で9年になりますが、このブログは府北部のものは少々UPしてきましたが、府南部のものはほとんどUPしていません。でも、それなり撮影しているので、徐々にUPしていこうかなと思います。当時はバラエティに富んでいたのを覚えています。
以上です。
レインボー
を4台投入しました。京都200か 166〜169です。166〜168が亀岡、169が舞鶴に新製配置されましたが、後ほど168が綾部へ転属し、その時点で旧京都交通が会社更生法の手続を行い、南部が京阪バス、北部が日本交通に譲渡されました。そのため、166と167が京阪京都交通、168と169が新京都交通へ引き継がれ、それぞれ離れ離れになってしまいました。


京阪京都交通に引き継がれた166と167です。京阪京都交通へ引き継がれた後、2006年に京阪バスカラーへ変更され、更に亀岡から中山(当時)へ転属し、現在に至っています。京阪バスカラーになったとはいえ、違和感なくまとまっています。とはいえ、既に京都交通カラーより京阪バスカラーの方が長くなってしまいました・・・。

旧京都交通時代の167です。当時は亀岡にいましたが、もっぱら亀岡ローカルで活躍していたため、京都駅に姿を見せる事はほとんど無かったようです(姿を見せていたのは大型車でしたが・・・)。10年前の亀岡駅バス乗り場は比較的狭かったのを思い起こします・・・。


京都交通に引き継がれた168と169です。京阪京都交通に引き継がれた車両は京阪バスカラーに変更されたに対し、京都交通に引き継がれた車両は現在も旧京都交通のままで活躍しています。今は廃車が進んで残り少なくなってしまいましたが・・・。168が福知山から舞鶴へ転属し、2台とも舞鶴で活躍しています。幕と社番以外は旧京都交通の面影を残しています。

旧京都交通時代の169です。169は新製配置時から一貫して舞鶴に配置されている舞鶴生え抜きです。当時も現在と変わらぬ姿で活躍していました。とはいえ、舞鶴管内では路線の再編成と廃止が進み、昔の面影も少なくなっています・・・。
運命とはいえ、同一事業者が投入した車両が会社更生法の適用に伴って別々の事業者へ別れてしまい、それぞれ別の姿になってしまいました。でも、それぞれ使命を背負って活躍していたのが印象的でした。
旧京都交通が無くなって今年で9年になりますが、このブログは府北部のものは少々UPしてきましたが、府南部のものはほとんどUPしていません。でも、それなり撮影しているので、徐々にUPしていこうかなと思います。当時はバラエティに富んでいたのを覚えています。
以上です。