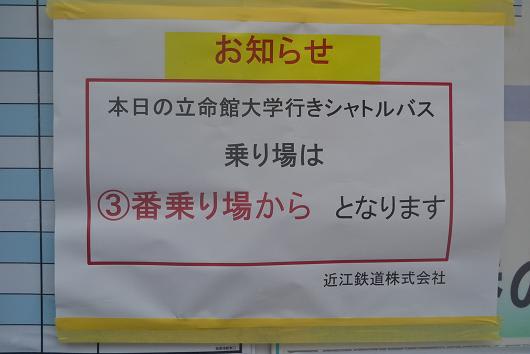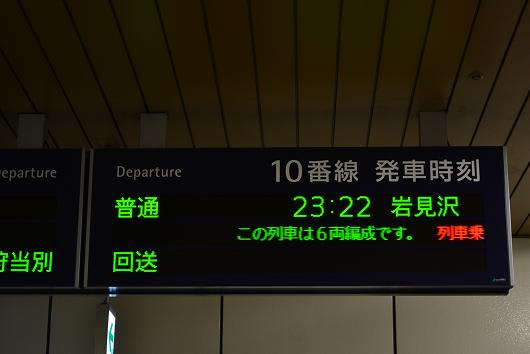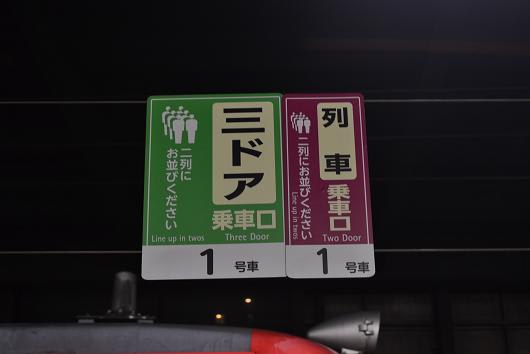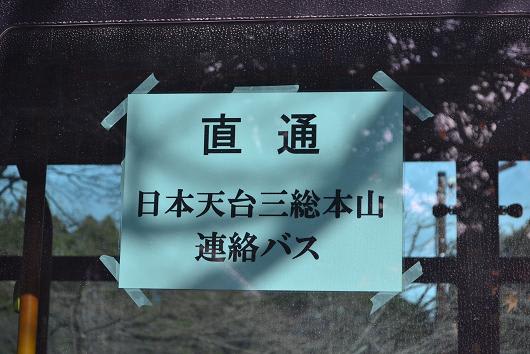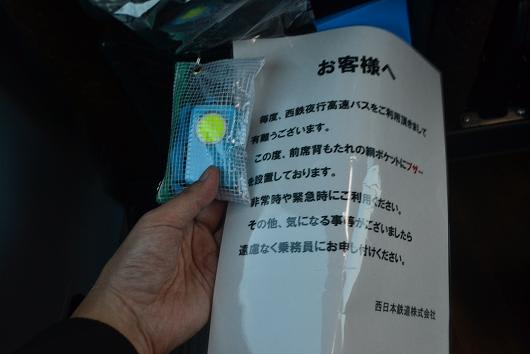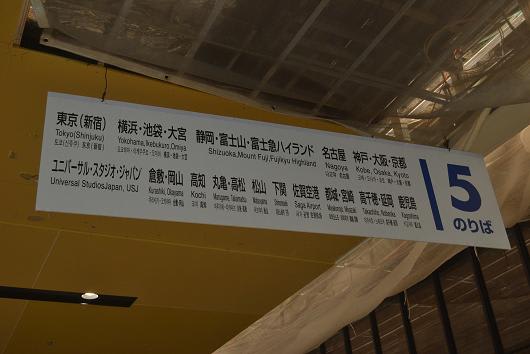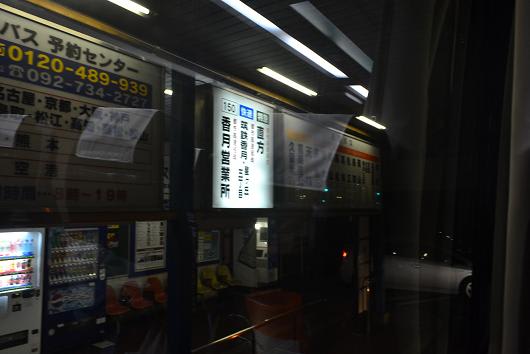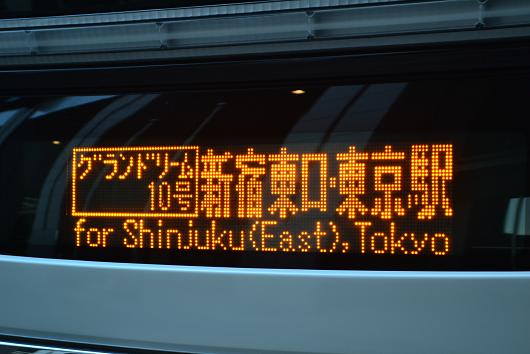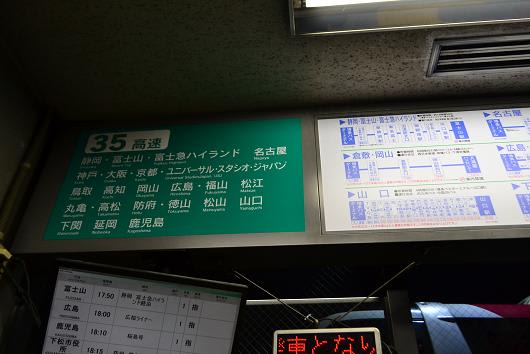11月23日に
つくばマラソン
が開催され、それに伴って関東鉄道バスは研究学園駅・土浦駅~会場間において臨時バスが運行されました。その臨時バスを撮影しましたのでレポートします。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
研究学園駅~会場
間のシャトルバスに充当された車両たちです。約40台が動員されていました。確認した営業所はつくば中央、土浦、つくば北、竜ヶ崎、水海道、取手、パープルバス、グリーンバス石岡でした。県南の各営業所から動員されていました。以下の充当された車両をUPしますが、数が多いため写真は一部にとどめます(☆が写真ありです)。
1号車 9361YT☆
2号車 9373YT☆
3号車 9281YT
4号車 9357YT
5号車 9314YT
6号車 1923YT
7号車 9374YT☆
8号車 9336TC
9号車 9380TC☆
10号車 9364TC
11号車 9291TC
12号車 2060TC☆
13号車 9354TC☆
14号車 9366TC
15号車 9365TC
16号車 9388TC☆
17号車 9323TC
18号車 9379TK
19号車 9286TK☆
20号車 9343TK☆
21号車 1922TK
22号車 2050MK
23号車 2051MK☆
24号車 9371MK
25号車 1823MK
26号車 9340MK☆
27号車 9372MK☆
28号車 1688RG☆
29号車 9283RG☆
30号車 9369RG☆
31号車 9319RG
32号車 9287RG
33号車 9312RG
34号車 2005TR☆
35号車 1877TR☆
36号車 P023☆
37号車 P022☆
38号車 P010
39号車 G037☆
40号車 G057
ほんとに多いですね・・・。そのおかげで未撮影車両もゴロゴロ出てきて、しっかりと撮影できました。でも、研究学園駅~会場間は約20分という距離ながらこんだけのバスが動員するほど参加者が多いとは驚きました。最近は市民マラソンが人気で、京都マラソンの凄さを知っていたものの、つくばマラソンもそれに劣らぬ人気とは驚きました。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
こちらは
土浦駅~会場
の臨時バスです。土浦駅東口発で、高架橋を通って会場に至るというものでした。担当は全て水戸でした。土浦駅発着なので土浦が担当するかと思いや全て水戸担当とは意外でした・・・。でも、研究学園駅発着よりも距離が長いのですが、人は多くなかったようで、台数も10台と少数でした。以下の充当された車両をUPしますが、数が多いため写真は一部にとどめます(☆が写真ありです)。
41号車 1869MT☆
42号車 1931MT☆
43号車 9320MT
44号車 1824MT☆
45号車 9332MT
46号車 1843MT
47号車 9276MT
48号車 9330MT
49号車 9297MT
50号車 9296MT☆
中型ロングを含む全て大型車でした。大型車のほとんどが動員されたため、当日の水戸駅発着路線は中型車ばかりでした・・・。土浦花火大会では10台も動員されることは無いので、マラソンのために10台とは驚きでした・・・。
![]()
![]()
![]()
![]()
こちらは
東京駅~会場
のバスです。これは路線ではなく、読売旅行が募集をかけた貸切バスとしての運行で、ヤサカバスなどの大手貸切業者の貸切バスが約15台以上来ていました。ほとんどがセレガーラでしたが・・・。
![]()
![]()
研究学園駅~会場間の臨時バスを担当していたつくば中央の車両の一部は臨時バスを2本運行した後、役員輸送に充当されていました。担当したのは1号車の9361YTから6号車の1923YTの6台で、それぞれ3台ずつ2ルートに分けて運行されていました。因みに7号車の9374YTは役員輸送に充当せず、引き続き臨時バスに充当されていたようです。
先日にtwitterでUPしましたが、39号車のG037が臨時バスを数本担当した後、筑波山シャトルバスの14号車として筑波山シャトルバスに充当されていました。当日は筑波山でもピークシーズンだったこともあり、多数の車両が応援に駆けつけていました(貸切車が中心でしたが・・・)。
![]()
臨時バスの降車場です。臨時バスの降り場と乗り場は陸上競技場周辺に設けられていました。尚、筑波大学構内の道路がコースとなったため、C10系統などは運休、10系統などは筑波メディカルセンター止まりで運行されていました。
![]()
![]()
臨時バス以外でも未撮影車両も撮影できました。上は元京成バスのエルガの9389TCです。9388TCとほぼ同時に入りましたが、9388TCは短尺+中扉が引戸、9389TCが標準尺+中扉が4枚折戸と仕様が異なっていました。元々いた営業所が違うとはいえ、京成バスは柔軟に仕様を変えていた証しですね・・・。下は土浦からつくば北へ転属した9318TKです。
以上です。
つくばマラソン
が開催され、それに伴って関東鉄道バスは研究学園駅・土浦駅~会場間において臨時バスが運行されました。その臨時バスを撮影しましたのでレポートします。




















研究学園駅~会場
間のシャトルバスに充当された車両たちです。約40台が動員されていました。確認した営業所はつくば中央、土浦、つくば北、竜ヶ崎、水海道、取手、パープルバス、グリーンバス石岡でした。県南の各営業所から動員されていました。以下の充当された車両をUPしますが、数が多いため写真は一部にとどめます(☆が写真ありです)。
1号車 9361YT☆
2号車 9373YT☆
3号車 9281YT
4号車 9357YT
5号車 9314YT
6号車 1923YT
7号車 9374YT☆
8号車 9336TC
9号車 9380TC☆
10号車 9364TC
11号車 9291TC
12号車 2060TC☆
13号車 9354TC☆
14号車 9366TC
15号車 9365TC
16号車 9388TC☆
17号車 9323TC
18号車 9379TK
19号車 9286TK☆
20号車 9343TK☆
21号車 1922TK
22号車 2050MK
23号車 2051MK☆
24号車 9371MK
25号車 1823MK
26号車 9340MK☆
27号車 9372MK☆
28号車 1688RG☆
29号車 9283RG☆
30号車 9369RG☆
31号車 9319RG
32号車 9287RG
33号車 9312RG
34号車 2005TR☆
35号車 1877TR☆
36号車 P023☆
37号車 P022☆
38号車 P010
39号車 G037☆
40号車 G057
ほんとに多いですね・・・。そのおかげで未撮影車両もゴロゴロ出てきて、しっかりと撮影できました。でも、研究学園駅~会場間は約20分という距離ながらこんだけのバスが動員するほど参加者が多いとは驚きました。最近は市民マラソンが人気で、京都マラソンの凄さを知っていたものの、つくばマラソンもそれに劣らぬ人気とは驚きました。





こちらは
土浦駅~会場
の臨時バスです。土浦駅東口発で、高架橋を通って会場に至るというものでした。担当は全て水戸でした。土浦駅発着なので土浦が担当するかと思いや全て水戸担当とは意外でした・・・。でも、研究学園駅発着よりも距離が長いのですが、人は多くなかったようで、台数も10台と少数でした。以下の充当された車両をUPしますが、数が多いため写真は一部にとどめます(☆が写真ありです)。
41号車 1869MT☆
42号車 1931MT☆
43号車 9320MT
44号車 1824MT☆
45号車 9332MT
46号車 1843MT
47号車 9276MT
48号車 9330MT
49号車 9297MT
50号車 9296MT☆
中型ロングを含む全て大型車でした。大型車のほとんどが動員されたため、当日の水戸駅発着路線は中型車ばかりでした・・・。土浦花火大会では10台も動員されることは無いので、マラソンのために10台とは驚きでした・・・。




こちらは
東京駅~会場
のバスです。これは路線ではなく、読売旅行が募集をかけた貸切バスとしての運行で、ヤサカバスなどの大手貸切業者の貸切バスが約15台以上来ていました。ほとんどがセレガーラでしたが・・・。


研究学園駅~会場間の臨時バスを担当していたつくば中央の車両の一部は臨時バスを2本運行した後、役員輸送に充当されていました。担当したのは1号車の9361YTから6号車の1923YTの6台で、それぞれ3台ずつ2ルートに分けて運行されていました。因みに7号車の9374YTは役員輸送に充当せず、引き続き臨時バスに充当されていたようです。
先日にtwitterでUPしましたが、39号車のG037が臨時バスを数本担当した後、筑波山シャトルバスの14号車として筑波山シャトルバスに充当されていました。当日は筑波山でもピークシーズンだったこともあり、多数の車両が応援に駆けつけていました(貸切車が中心でしたが・・・)。

臨時バスの降車場です。臨時バスの降り場と乗り場は陸上競技場周辺に設けられていました。尚、筑波大学構内の道路がコースとなったため、C10系統などは運休、10系統などは筑波メディカルセンター止まりで運行されていました。


臨時バス以外でも未撮影車両も撮影できました。上は元京成バスのエルガの9389TCです。9388TCとほぼ同時に入りましたが、9388TCは短尺+中扉が引戸、9389TCが標準尺+中扉が4枚折戸と仕様が異なっていました。元々いた営業所が違うとはいえ、京成バスは柔軟に仕様を変えていた証しですね・・・。下は土浦からつくば北へ転属した9318TKです。
以上です。