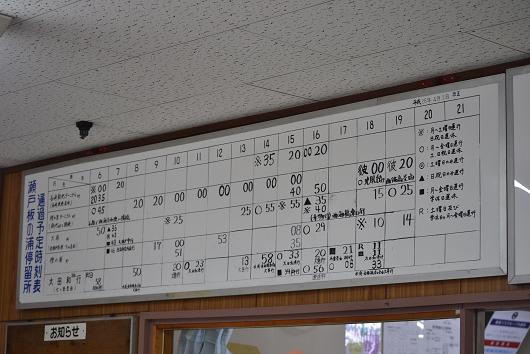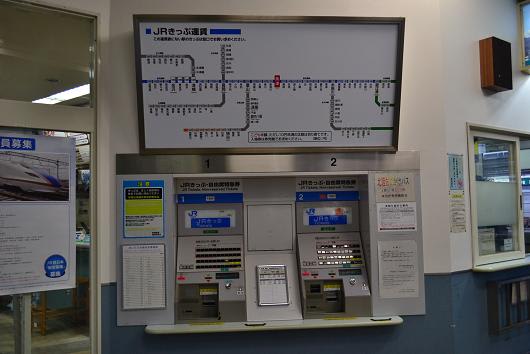12月に滋賀県内の各駅前にある
平和堂
巡りをレポートしましたが、その1(東海道本線編)に引き続いて湖西線・北陸本線沿線をレポートします。湖西線は東海道本線より沿線人口が少ないこともあり、店舗数も少なく、出店も1970年代後半からと湖西線開業以降となっています。しかし、地元の商店街や小売店と共存を図る取り組みを行うなど新しい施策が目立っていることもポイントです。北陸本線沿線も湖西線同様に沿線人口が少ないため、店舗数は多くありませんが、福井県など滋賀県外の沿線にも店舗を構えるなどしています。今記事では特別に滋賀県外の店舗をいくつかUPします。
1.比叡山坂本駅
![]()
湖西線に入って最初に来る駅が
比叡山坂本駅
です。比叡山延暦寺への玄関口そして日吉大社の最寄り駅でもあります。
![]()
その比叡山坂本駅から湖西線に沿って少し北へ行くと、
平和堂坂本店
があります。1993年5月に開店した比較的新しい店舗です。ヤマダ電機など一部の専門店が入居しているので、アルプラザ型店舗です。そのため、アルセという名前も付いています。1980年代から見られるようになった典型的な中型店舗で、3階建てで、4階以上は駐車場です。
因みに大津京駅は駅近くにイオン(旧ジャスコ)が1996年に開店していますが、大津に平和堂や西友や西武など多数の大型店舗が出店している事もありイオンが開業するまで大型店舗はありませんでした。でも、2012年に旧競輪場の近くにフレンドマートが出店しています。
2.堅田駅
![]()
次は湖西線最大の駅である
堅田駅
です。堅田は湖西地区で一番大きな街で、大津市になっているとはいえベッドタウン化が進むなど人口が少しずる増えています。堅田と守山を結ぶ琵琶湖大橋もその近くにあります。
![]()
その堅田駅の琵琶湖側に
アルプラザ堅田店
があります。アルプラザ堅田店は平和堂堅田店として1978年7月に開店しました。これが湖西線沿線初の出店となります。しかし、建物の老朽化によって建て替えの上2008年にアルプラザ堅田として開店しました。アルプラザ堅田の前身である平和堂堅田店は地元の商店が1~2階に入店した事がポイントで、大型店と地元商店がドッキングしたとして注目を集めたそうです。
店舗そのものは典型的なアルプラザ型です。でも、典型的なアルプラザ型としては現時点で最新の店舗で、最近は食料品に特化したフレンドマート化が進んでいるだけに今後はどうなるんでしょうね・・・(もしかしたら、最後のアルプラザになるかも・・・)。まぁ、2008年に開業しただけに最新のデザインや設備が揃っています。
![]()
江若交通のバスの撮影をしていて、たまたま平和堂堅田店が写った写真がありましたので、UPします。写真の左側にちょっと写っている建物が平和堂堅田店です。堅田店は5階ほどまであるごく普通な総合スーパーの建物でした。中に入った記憶はあるのですが、どのような感じだったのかは忘れました・・・。
3.和邇駅
![]()
堅田の次は堅田から2駅目の
和邇駅
です。
![]()
和邇駅のすぐ近くの線路沿いに
平和堂和邇店
があります。平和堂和邇店は1984年9月に開店しました。典型的な中型店で、一部の地元商店が入居しており、そのためにアルタとう名称が付いています。外のアルタの看板にワニのキャラクターがある辺りも和邇らしいですね・・・。店は3階建てですが、少々寂しい感じでした。でも、最近は閉店しがちなレストランが営業中なのはさすがに驚きました・・・。
因みに和邇店は大津市で最北端の平和堂店舗です。
![]()
3Fにはプレイランドが設けられているのですが、一部には家庭ではほぼ見られなくなったブラウン管がまだ置かれていましたが、故障中で使えなくなっていました。以前に故障して長らく放置中なのが正しいようですね・・・。因みに鉄関係はありませんでした。
4.安曇川駅
![]()
和邇駅の次は暫く飛んで
安曇川駅
です。安曇川駅は旧安曇川町の中心駅です。
![]()
安曇川駅東口を出て、琵琶湖方面へ少し歩いた先の国道161号線沿いに
平和堂あどがわ店
があります。平和堂あどがわ店はかって平和堂安曇川店でしたが、安曇川店の建物が老朽化したため、2008年に国道161号線沿いへ新築移転し、平和堂あどがわ店として開業しました。最近はアルプラザ型もしくはフレンドマート型として出店する事が多く、純粋たる平和堂としてはあどがわ店が最新で、あどがわ店自体も1990年代以来約10年ぶりとなるとか・・・。
さて、店舗ですが、平和堂といいながら1階建てになっている事がポイントで、その1階建てに食料品、衣服品、日用品などが色々入っており、更にダイソーやTSUTAYAなどのチェーン店も入店しています。最近は大型店でも中心部からやや外れたところに広い敷地を確保し、1~2階建ての建物を建てるという形が広がっており、平和堂もそれに習った感じです。時代の流れに沿った感じでしょうか・・・。
因みにその3で紹介予定ですが、2014年に開業したフレンドマート日野店も同じような形態です。
![]()
![]()
あどがわ店にはプレイランドもあるのですが、そこには205系や100系の遊戯物が置かれていました。おそらく、平和堂安曇川店から持って来たのだと思います。
![]()
![]()
こちらは2008年にあどがわ店への移転に寄って閉店された
平和堂安曇川店
です。平和堂安曇川店は1978年10月に湖西地区の第2号店として開業しました。その安曇川店は地元の小売店と共存を図り、薬や書籍などの一部商品は平和堂に隣接したアスピーで販売し、地元小売店で取り扱わないものは平和堂で販売するという形でした。堅田とは内容が違うものの地元の商店と共存を図っている事は同じでした。でも、時代の流れで客足が大型店へ向かい、結局は全て平和堂で取り扱うようになっていたようです・・・。
そんな安曇川店ですが、老朽化によって2008年に閉店し、国道161号線沿いへ移転しました。閉店後も建物はそのまま残っていましたが、2014年に解体されました。
![]()
安曇川駅のホームから見た平和堂です。安曇川店は駅のすぐそばにありました。しかし、あどがわ店は駅から少し離れた国道161号線沿いにありますが、駅からも鳩マークがよく見えます。つまり、写真では2つの鳩マークが見える形ですね・・・。
5.近江今津駅
![]()
安曇川駅の次は
近江今津駅
です。湖西線の運転上の拠点駅の一つで、かっては京都方面の列車の多くはここまでで、ここで敦賀方面の列車に乗り継ぐ必要がありました。
![]()
近江今津駅から湖西線沿いを少し北へ行ったところに
平和堂今津店
があります。平和堂今津店は1993年11月に開業しました。坂本店と同じく比較的新しい店舗ですが、一部は地元の商店が入居しており、リフレという名称も付いています。最近はJoshinも入っています。店は2階建てです。
その今津店は湖西線沿線で最北端の平和堂店舗で、それより北はありません。
![]()
平和堂は近江今津駅から歩いて10~15分ぐらいしたところにあるのですが、平和堂の前には湖国バスの北浜(平和堂前)バス停があり、駅からバスで行くこともできます。しかし、本数が少ないです・・・。撮影時はたまたまバスが来たという事で・・・。
6.長浜駅
![]()
次は北陸本線です。米原を出て最初に来るのが
長浜駅
です。長浜は滋賀県北部の中心的なところで、豊臣秀吉が一時期居城としていた長浜城などがあり、秀吉ゆかりの場所でもあります。鉄道でも明治期は鉄道と琵琶湖水運との接続駅、そして2006年までは直流電化の終端駅として機能するなど文字通りの鉄道の町でもありました。
![]()
![]()
長浜駅の向かい側に
平和堂長浜店
があります。平和堂長浜店は1969年11月に平和堂第3号店として開業しました。平和堂は彦根、草津に次ぐ新しい店舗を長浜に定めた辺り、鉄道の町で賑わっている点を考慮したのかもしれませんね・・・。1969年と言えば湖西線が開業する前で交直流デッドセクションが坂田~田村にあった頃でED70形などが活躍していた時期です。平和堂の建物はこんな時からずーっとあったわけですね・・・。建物そのものは5階建てで初期の総合スーパー形態を残していますが、テナントの撤退が進み、空きテナントが多くなっている階もあります。そこにはエスカレーターがあるのですが、上りの片道のみで、下るには階段を降りないといけないという今となっては珍しい構造です・・・。
そこで、正面に注目してください。5階に「スカイレストラン」の文字が見えます。昔は高いところで景色を見ながら食べるというスタイルが理想的に感じた時代だったので、その文字を見るだけでもかってこんなだったんだなと感じさせました。
![]()
しかし、そのレストランは最近まで営業していましたが、つい閉店となってしまいました。長浜店ではこのレストランともう一つうどん店も5階にありましたが、つい最近閉店し、飲食店が無くなってしまいました。
![]()
そんな長浜店ですが、建物の老朽化によって移転新築する事になり、現時点で長浜駅の側に新しい店舗を建設しています。新店舗は平和堂ではなくフレンドタウン長浜店となるようです。開店は2015年1月と告知されているようですが、具体的な開業日が出ていない・・・。現長浜店はフレンドタウン長浜店開業後に閉店し、解体する予定の事です。長浜店が無くなると、平和堂本来の総合スーパー形態を残す最古の店舗は我が地元の石山店になります。
長浜駅から少し離れた国道8号線沿いにアルプラザ長浜店がありますが、ここでは取り上げません。
7.木ノ本駅
![]()
長浜駅の次は
木ノ本駅
です。
![]()
![]()
木ノ本駅を北陸本線の踏切を渡って少し歩くと
平和堂木之本店
があります。平和堂木之本店は1985年に開業しました。滋賀県最北端の平和堂店舗でもあります。駅は木ノ本ですが、地名は木之本で、店舗名も地名に従って木之本となっています。木之本店は1980年代に開業しており、その時期に開店した店舗に多く見られる中型店というような位置づけで、2階建てとコンパクトになっています。でも、屋根の一部に瓦を使用するなど独特な雰囲気がありますね・・・。
![]()
そんな平和堂木之本店ですが、他の店舗にない特徴があります。これは食料品売り場と他の売り場で建物が別れていて、しかも両方つがなっていない事です。つまり、食料品売り場(食品館)と他の売り場を行き交うには一旦外に出る必要があります。どういったいきさつでそのようになったのかは不明ですが・・・、見るには最初は1つの建物でコンパクトにまとめていたものが売り場面積の増加に合わせて食品館だけ別建物として分けたのかもしれません・・・(食品館だけをみるとフレンドマートにも見えますが・・・)。
![]()
2階にプレイランドありますが、そこには電車でGOの乗り物が・・・。こういう乗り物一部の店舗で見かけますね・・・。
8.敦賀駅
![]()
滋賀県は木之本店で終わりなので、特別として滋賀県外に出ます。その最初は
敦賀駅
です。敦賀駅は福井県南部の最大の駅で、小浜線が接続し、更に敦賀地域鉄道部があるなど鉄道の拠点として機能しています。
![]()
敦賀駅から駅前通りを少し歩いた白銀交差点に
アルプラザ敦賀
があります。アルプラザ敦賀は平和堂敦賀店として1973年10月に開業し、2000年12月に建て替えの上にアルプラザ化したものです。平和堂敦賀店は平和堂の第8号店かつ滋賀県外初出店
でした。その敦賀店をきっかけに滋賀県外へ積極的に店舗を展開していくことになるのです。アルプラザ敦賀は6階建てですが、店舗は1~3階で、4・5階が駐車場、6階が映画館やレストランやプレイランドが入っています。立体駐車場が建物の上ではなく建物の中にある点が珍しいです。
9.武生駅
![]()
敦賀駅の次は
武生駅
です。武生市の中心駅で、福井鉄道と接続しています。
![]()
武生駅の側に
アルプラザ武生
があります。アルプラザ武生は平和堂武生店として1973年に開業した、2000年3月に建て替えの上にアルプラザ化したものです。武生店は平和堂の第9号店でした。敦賀とは異なり、4階建て(店舗は3階まで)とコンパクトになっている事がポイントです。でも北陸本線に沿って建てられているため、建物自体が細長くなっています。写真はJR武生駅側ですが、その反対側には福井鉄道越前武生駅があり、アルプラザ武生はJRと福井鉄道に挟まれていると見てもよさそうです・・・。
![]()
3Fにプレイランドがあり、そこには100系新幹線電車の乗り物が置かれていました。
10.小杉駅
![]()
次は
小杉駅
です。小杉駅は富山県にありますが、たまたま訪問できたのでUPします。
![]()
![]()
小杉駅南口すぐに
アルプラザ小杉
があります。アルプラザ小杉は1996年に富山県の第1号店として開業しました。小杉駅南口を出るといきなりアルプラザの駐車場が広がり、富山方に店舗があります。これは元々工場の敷地だったものが工場の閉鎖により平和堂が借り上げてアルプラザを出店した形です。店舗は2階までで、3階以上は立体駐車場です。これは典型的なアルプラザ型店舗ですが、ポイントとしてレストランだけが別の建物になっている事です。
![]()
![]()
小杉駅南口からは飲食店街の前の通路を歩くと店の中に入る形になっています。つまり、駅のすぐ近くという事になりますね・・・。そして、アルプラザから駅の入口には平和堂の標準文字で「JR小杉駅」と書かれた看板が掲げられています。でも、3月14日にはJRから第3セクターになってしまいますね・・・。
小杉駅南口はアルプラザのために設けられたのですが、アルプラザの存在によって本来の出入口である北口より南口の方が賑わっているという状況になっています。
以上です。湖西線と北陸本線は東海道本線沿線と比べると、沿線人口が少ないため、店舗も少ないです。でも、1978年に開業した堅田・安曇川店によってドミナント戦略が一応完成した事になっています。つまり、湖西線沿線は店舗展開が遅れていたという形ですね・・・。でも、ドミナント戦略が完成すると、東海道本線沿線では人口の少ない地域にも中型店を展開するなどさらなる出店が進んだに対し、湖西線と北陸本線沿線は更なる出店があまり進まず、新たに中型店が和邇、今津、木之本に出店したぐらいです。でも、ポイントなのが湖西線・北陸本線では今津店とアルプラザ長浜を除いてみんな駅前に店舗を構えてきた事です。湖西線沿線では琵琶湖と山地との間が狭く、国道も湖西線にほぼ並行しているという環境面と駅前に設ける事で周辺地域から電車を使って買い物に来れるようにするといった戦略面が交っているのかもしれません・・・。
次回はその3(草津線、近江鉄道など編)です。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()