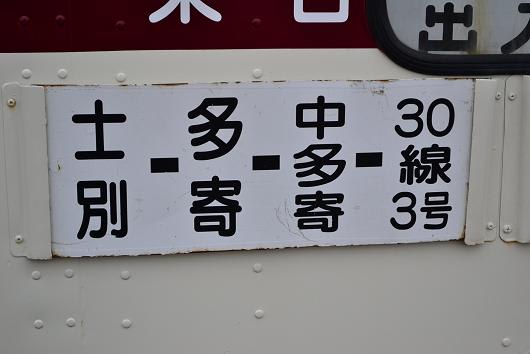滋賀県内を鉄道で通っていると、各駅の近くに屋上に鳩マークを掲げた建物をお目にかかった方が多いかと思います。その建物は滋賀県を中心に近畿・東海・北陸に店舗を展開している総合スーパー大手の
平和堂
です。平和堂は1953年に彦根市で創業して以来、滋賀県各地に店舗を展開しており、滋賀県民にとってはなじみ深いスーパーでもあります。私も気付けばかなりお世話になっていました。
そんな平和堂ですが、ドミナント戦略によって店舗を増やしていったため、滋賀県内の鉄道路線に乗っていると多くの駅の近くに平和堂の店舗を見かけることがよくあります。その各鉄道駅と近くにある平和堂をその1(東海道本線編)、その2(湖西線・北陸本線編)、その3(草津線、近江鉄道など編)の3回に分けてレポートしていきます。
レポートに入る前に平和堂の基礎知識及びレポートにあたっての定義を述べます。
平和堂は店舗拡大していく中でさまざまな出店パターンを取っていたため、店舗形態は大きく分けて3つあります。
平和堂・・・ごく一般的な総合スーパー形態
アルプラザ・・・総合スーパーに専門店を加えたもの
フレンドマート・・・食料品+αに特化したもの(住宅地の中にあるごく普通なスーパーと同じ)
このレポートでは基本的に総合スーパー形態とし、ごく普通のスーパーであるフレンドマートは対象外とします(例外あり)。平和堂といっても店舗縮小などでフレンドマートと変わらない状態になっている店もあるのですが、とりあえず対象としております。
まず、東海道本線沿線からです。東海道本線沿線は大津~米原間で近くに平和堂が無い駅を数えた方が早いほどたくさんあります。
1.大津駅
![]()
滋賀県に入って最初に来る駅が
大津駅
です。駅の近くに県庁があり、滋賀県の中心部とも言えます。
![]()
その大津駅の側に
アルプラザ大津
があります。アルプラザ大津は平和堂大津店として1974年に開業し、1986年にファッション品を強化したESTA(エスタ)に改称し、1994年に食料品も強化して現在のアルプラザになりました。アルプラザは新規開業もしくは既存平和堂店舗を新築移転したものがほとんどで、既存店舗をそのままアルプラザ化したのは大津店が唯一です。
しかし、客の減少と建物の老朽化により、2013年末をもって閉店する予定でしたが、諸事情で閉店が延期になっています。因みに閉店して建物を解体し、新たにマンションを建設し、その1階にフレンドマートとして入居する予定と聞いています。
現在は閉店を前提にテナントの撤退が進み1Fに衣服、B1Fに食料品が営業しているだけです。2F以上は閉鎖されましたが、B1・1Fにトイレが無い関係で2Fはトイレのためにごく一部が開放されている程度です。
![]()
![]()
アルプラザ大津店の特徴として、駅舎と店を直結する通路がある事です。平和堂は基本的に駅前もしくは駅から離れた場所にあるため、駅舎から一旦駅前広場に出る必要があります。しかし、アルプラザ大津店は改札口すぐにある階段を上るとアルプラザ大津への連絡通路に入り、そのままアルプラザ大津の2Fに行く事が出来ます。そういう連絡通路がある店はここだけです。
しかし、現在は大津駅の2Fが閉鎖され、更にアルプラザも2Fのほとんどが閉鎖されたため、連絡通路も閉鎖されています。連絡通路の案内が「平和堂」になっていて、かって平和堂だった名残りになっています。
2.石山駅
![]()
次の膳所駅は近くに平和堂が無いので、次は私の地元の
石山駅
となります。石山駅は滋賀県下の駅で最大乗降数を誇る駅です。
![]()
その石山駅から徒歩5分ぐらいした商店街の中に
平和堂石山店
があります。平和堂石山店は1970年9月に平和堂第4号店として開業しました。石山店は典型的な総合スーパー形態で、初期の店舗形態を残す数少ない店舗です。最近の平和堂は環境変化などによりチェーン店の受け入れが増えているのですが、石山店はダイソーといったチェーン店が入居している程度で、大半の売り場が平和堂直営のままとなっている事がポイントです。
そんな石山店ですが、石山駅周辺に雑貨店がほとんどないため、日用品などを買いに行く時に時折重宝しています(たまに食料品も・・・)。私にとって生活の一部とも言えましょうか・・・。何気なく利用してきた石山店が滋賀県に多数ある平和堂の第4号店と知った時は驚いたものです。
![]()
平和堂石山店で最大のポイントは何ともいっても5Fです。5Fはゲーセンとレストランがあるのですが、ゲーセン部分はかってボーリング場でした。しかし、石山駅近くの国道1号線沿いに大きなボーリング場が出来ると、そちらへ客が行ってしまったためにボーリング場が閉鎖され、床をかさ上げした上でゲーセンに転用されました。でも、ゲーセン部分の床が一段低い状態なので、ボーリング場の名残りを残しているとも言えましょうか・・・。国道沿いのボーリング場の方は10年ぐらい前に閉店され、今はマンションが建っています。
しかし、今年の秋にゲーセンが閉鎖され、遊戯類が全て撤去され、広大な空きスペースになっています。
3.瀬田駅
![]()
石山駅の次の駅の
瀬田駅
です。
![]()
瀬田駅から少し草津方面へ歩くと
アルプラザ瀬田
があります。アルプラザ瀬田は1987年2月に開業しました。バブル期に開業したせいか、高級的なデザインが特徴で、特にエレベーターが凄いです。そして、国道1号線沿いにあるため、大型の立体駐車場が設けられています。そこまでいいのですが、客減少でテナントの撤退が進み、今はTSUTAYAが入居するなどテコ入れを図っています。開業間もない頃に行った記憶があるのですが、当時は屋上に遊園があり、所々賑わっていたような記憶があります。しかし、今は屋上は閉鎖され、4Fは塾などが入居しており、上はやや元気のない様子でした。
![]()
3Fにはプレイランドが設けられており、そこには約15年前にブームとなった電車でGO!が置かれています。15年前は凄いブームで、草津などのゲーセンに置いてあったのを覚えています。今はほとんどのゲーセンから撤去され、プレイランドを中心に僅かに残っているにすぎません。実を言うと、電車でGO!が置かれている平和堂店舗はもう一つあるのですが、これは後ほど・・・。
4.草津駅
![]()
瀬田駅の次の南草津駅は平和堂は無いので(駅の近くにフレンドマートがあるけど・・・)、その次の
草津駅
です。草津駅は東海道本線と草津線が分岐する交通の拠点です。昔は宿場も設けられていましたね・・・。そのため、昔から駅周辺に平和堂、ヒカリ屋、近鉄百貨店などが出店し、競合していました。
![]()
草津駅東口を出て、駅前広場を挟んで向かい側に
くさつ平和堂
があります。くさつ平和堂は平和堂草津店として1968年に開業しました。平和堂の第2号店で、この草津店の開店により琵琶湖ネックレスチェーン展開が本格的に始まりました。開業から50年以上たっているにもかかわらず建物の古さを感じさせないのは2000年に大幅改築を行ったためです。しかし、内部はテナントの撤退が進み、実質的に1Fの食料品、2Fの衣服のみの営業で、3Fは本屋などの専門店、4・5Fは塾が入居しています。なので、総合スーパーとしての機能はほぼ失われたという感じでしょうか・・・。
![]()
駅側の正面出入り口です。外観が目新しいのですが、大幅改装した結果なんですが・・・。でも、大幅改装は客減少の苦境から延命した形ですが・・・。
![]()
東口の反対側にあたる西口から少し歩くと
アルプラザ草津
があります。これは大型商業施設のエイスクエアの中にあり、1996年に開業しました。このアルプラザ草津の開業により平和堂とエルティ932の客がそこへ転移し、平和堂とエルティ932は店舗縮小を余儀なくされました。まさに厳しい競争ですね・・・。特にエルティ932の全盛時代を知っているだけに現状をみると目を覆いたくなります・・・。
さて、アルプラザ草津は2階建てですが、店は平面に大きく広がっており、いくつかの専門店が入っています。建物外にも専門店があり、これらでエイスクエアを構成しています。イオンモールなどが出来た今でも賑わいはほぼ持続している事は嬉しい限りです。
5.栗東駅
![]()
草津駅の次の
栗東駅
です。1991年に開業した比較的新しい駅です。
![]()
栗東駅の向かい側に
アルプラザ栗東
があります。これは2003年に開業したものですが、かっては栗東サティでした。しかし、サティを運営しているマイカルが破たんしたため、閉店する事になり、その店舗跡を平和堂が買い取ってアルプラザとして開業しました。ただ、アルプラザとして開業するための改装が短期間であったため、平和堂らしくない所がいくつか見られます。店自体は3階建てで、平和堂店舗と専門店が入っています。実は栗東サティ時代に行ったことあるのですが、ほとんど覚えてないなぁ・・・。
![]()
![]()
アルプラザ栗東のアミューズメントにはN700系の乗り物が置かれていました。デパートのアミューズメントには新幹線などの乗り物が置かれているところが多いのですが、時代の変化に合わせて車両そのものも変化してきていますが、最近はN700系まで出てきているようです。そのN700系はLCD画面付きです。変わったなぁ・・・。
6.守山駅
![]()
栗東駅の次の
守山駅
です。
![]()
守山駅西口を出て、少し歩くと
平和堂守山店
があります。1976年に開業しました。平和堂は駅~歩いて数分のところにあるのですが、駅からは見えません。平和堂周辺が高層マンションに囲まれているためなのですが、高層マンションはほとんどが近年に建設された新しいものばかりです。その中にやや古い建物が建っている自体が守山の発展を感じさせます。守山店は総合スーパー形態ですが、飲食店はありません。因みに開業時の写真がネットに出ていたのですが、建物そのものはそのままで、色だけ違っていました・・・。
因みに守山駅から離れた西の方にアルプラザ守山があるのですが、対象外とします。
![]()
守山店は店舗と駐車場が道路を挟んで別の建物になっており、これをつなぐ通路があります。こういうものはアルプラザ瀬田でも見られますが、道路をはさんでというのはあまり見かけないような・・・。
7.野洲駅
![]()
守山駅の次の
野洲駅
です。野洲駅には網干総合車両所野洲派出所があり、一部の列車はここを起終点としているほど列車運行上の拠点となっています。
![]()
野洲駅東口を出て少し歩いた新幹線高架橋の側に
アルプラザ野洲
があります。2000年に平和堂野洲店を移転した上でアルプラザ化して開業しました。平和堂野洲店は平和堂第6号店として1971年に開業しているので、老朽化のためだと思われます。2階建てで、いろんな専門店が入っています。隣に新幹線が通っているので、新幹線の車窓からすぐ近くに平和堂のハートマークが出て来たのを見たお方が多数おられるかと思います。
![]()
アルプラザ野洲の前に野洲市コミュニティバスが通っています。アルプラザの買い物客がコミュニティバスを利用している方がおられました。尚、一般路線はアルプラザ手前の道路を通るだけであるプラザには立ち寄りません(バス停も近くになし)。
8.篠原駅
![]()
野洲駅の次の
篠原駅
です。滋賀県に入って東海道本線の各駅は橋上駅舎が続いていましたが、篠原で初めて地上駅舎と出会う事になります。小さな駅舎というのはのどかな印象がありますね・・・。
![]()
篠原駅から近江八幡方面へ少し歩くと
平和堂篠原店
があります。1990年に開業しました。平和堂は1980年代から店舗展開に当たって売り場面積をやや小さめにしていますが、篠原店はその仲間にあたります。従って、売り場は食料品、衣服、日用品と生活に必要な最低限のものが並べられています。篠原店の特徴として、1階が駐車場&専門店、2階が食料をはじめとする平和堂店舗であることがポイントです。そのため、1階から2階へは長いスロープが設置されています。平和堂でこういう形になっているのは少ないですね・・・。
![]()
3階にはかってちびっこ広場と称するプレイランドがありましたが、プレイランドそのものが閉鎖され、一部を除いて物置になっています。平和堂では中型店でもこういうプレイランドが折られていましたが、最近は閉鎖が続いているようです。
9.近江八幡駅
![]()
篠原駅の次の
近江八幡駅
です。近江八幡市の中心駅で、草津以北の琵琶湖線で乗客の多い駅です。また、ここから近江鉄道線が分岐しています。
![]()
近江八幡駅北口の向かい側に
平和堂近江八幡店
があります。1972年に開業した平和堂第7号店です。現存する平和堂で言うと5番目に古いものですね(第5・6号店は現存していない)。この店は総合スーパー形態が基本ですが、テナントの撤退や入れ替わりが進んでいます。確か、3F(だったと思う)に家具店が階全体に入居しています。
![]()
![]()
平和堂近江八幡店を語るには外せないのが5Fにある鉄道運転模型「交通パノラマ」です。これは平和堂の創業者が趣味で設置したものです。これは以前に拙ブログの記事にてレポートしていますので、詳しくはそちらをごらんください。
http://blog.goo.ne.jp/yoichiro1221_train223kei/e/0a9d2529590f74f4d2c2567cfdd8617c
因みに小さい頃に訪れた事があり、当時は交通パノラマ館だけでなく、鉄道の前面展望を楽しめるゲーム機械もおかれていた記憶があります。それだけに昔は鉄分満載なプレイランドでした。今はプレイランドすら閉鎖してしまい、5Fは鉄道模型と飲食店1軒があるだけというさびしい状態になっています。
![]()
近江八幡駅からちょっと歩いた先にある近江八幡市役所近くに
アルプラザ近江八幡
があります。これは元々ダイエーだったものを閉店後に平和堂が買い取って2007年にアルプラザとして開業したものです。因みにダイエー近江八幡店は滋賀県初のダイエー店舗でしたが、閉店により滋賀県からダイエーが無くなっています。このアルプラザは3Fに電気店のエディオンが入居している以外は基本的に典型的なアルプラザ形態です。私が中学生の頃、近江八幡で開催された駅伝大会に参加した時、その打ち上げ会のためにダイエー近江八幡店に行った記憶があります。
10.能登川駅
![]()
近江八幡駅の次は一駅飛んで
能登川駅
です。
![]()
能登川駅西口に
フレンドマート能登川店
があります。本来なら対象外ですが、駅前にあるという事でちょっと取り上げます。フレンドマート能登川店は2003年に能登川駅の改装に合わせて平和堂能登川店(1977年開業)を移転してフレンドマート化したものです。ただ、フレンドマートといっても、TSUTAYAなどが入居しており、実質的に総合スーパー形態に近い感じになっています。
ただ、老朽化した平和堂店舗の移転新築などに合わせてフレンドマート化するという動きがいくつか出ているので、能登川のようなケースが出てくるのかもしれません。
10.河瀬駅
![]()
能登川駅の次は一駅飛んで
河瀬駅
です。
![]()
河瀬駅西口から琵琶湖線沿いを北へ向かい、県道196号線を北西へ向かうと、
平和堂日夏店
があります。河瀬駅近くの平和堂は河瀬店でなく、日夏店となっています。これは平和堂の所在地が日夏町である事から来ています(河瀬駅は南河瀬町)。1991年に開業した中型店で、2階建てとなっています。篠原店と同じように駅からちょっと歩いたところに平和堂が位置しているのは駅周辺の住民や駅からかなり離れたところの住民の両方をカバーできるようにしているためです。駅からちょっと離れた場所に中型店を開店するのは1980年代から1990年代にかけての特徴です。
11.南彦根駅
![]()
河瀬駅の次は
南彦根駅
です。周辺のベッドタウン化に伴って1981年に開業した比較的新しい駅です。
![]()
南彦根駅東口から歩いてすぐのところに
ビバシティ彦根
があります。これは平和堂が「京滋最大級の大型複合商業施設」として1996年に開業しました。アルプラザを上回る大型商業施設で、3階建ての建物に平和堂店舗をはじめ多数の専門店街にボーリング場、映画館などの娯楽施設が入っています。最近各地で開業が相次いでいるイオンモールと似た形態です。滋賀県では守山市にピエリ守山、竜王町に三井アウトレットパーク、草津市にイオンモール草津などの開店が相次いでいますが、ビバシティはその先駆けに当たります。しかも、滋賀県北部における大型商業施設はビバシティが唯一なので、開業から15年以上経った現在も盛業中です。
開店当時、ビバシティの近くに住む私の友人がビバシティのことについて色々話をされていて、かなり離れた滋賀県南部に住む私にとって羨ましく思ったものです(当時の世間話はビバシティの話で持ちきりでした)。でも、私は次の年にその友人の家へ遊びに行くついでに初めてビバシティに行きました。その時は圧倒的な広さにビックリの連続でした。
![]()
ビバシティのプレイランドにはN700系の乗り物が置かれていました。アルプラザ栗東と同じものですね・・・(形は多少違いますが・・・)。
![]()
ビバシティの隣には
平和堂本部
があります。つまり、平和堂の本社ということになります。平和堂は彦根で創業しており、それ以来ずーっと彦根に本部を構えています。ビバシティと比べると地味ですが、これでも滋賀県を中心に近畿、北陸、東海そして中国に店舗を展開しているのだから・・・。
12.彦根駅
![]()
南彦根駅の次は
彦根駅
です。近江鉄道と接続している滋賀県北部の中心を成す駅です。
![]()
彦根駅西口の駅前広場の向かい側に
アルプラザ彦根
があります。これはアルプラザの第1号店として1979年に開店しました。平和堂は総合スーパー形態ですが、アルプラザは総合スーパー形態を基本に専門店を充実化した事がポイントです。アルプラザは一般的に駅から少し離れた広い土地に3階建てという構成が基本なのですが、開店当時は駅前に4~5階建てという構成が基本であったため、アルプラザとしては珍しく6階建てとなっています。珍しいというか初期の平和堂の形そのものになっている感じでしょうか・・・。とはいえ、最近はテナントの撤退が少しずつ進んでいて、特にレストランは1~2店のみと他の平和堂並みになっています。
因みに彦根駅から少し離れた銀座商店街に彦根銀座店がありますが、これは最寄り駅が近江鉄道ひこね芹川駅であるため、その3にて紹介します。
![]()
![]()
アルプラザ彦根では6Fに
鉄道模型店
があり、広大なジオラマがあります。多数の鉄道模型が展示されており、運転する事も出来ます。平和堂近江八幡店と並んで鉄道ファンにはオススメなポイントです。
13.米原駅
![]()
彦根駅の次は
米原駅
です。東海道本線と北陸本線が分岐する昔からの鉄道の拠点で、更に新幹線や近江鉄道と接続しています。まさしく鉄道によって栄えた町です。
![]()
新幹線側の米原駅西口の駅前広場の向かい側に
平和堂米原店
があります。平和堂米原店は1986年に開店しましたが、当時の形態に沿った3階建ての中型店となっています。とはいえ、テナントの撤退や入れ替わりが進んでいるのですが、1Fのフードコートが特にさびしくなっています(かってはマクドナルドあったのに無くなってしまったし・・・)。そして、3Fには時間制のプレイランドがあり、電車でGO!が置かれています。平和堂で電車でGO!が遊べるのはアルプラザ瀬田と平和堂米原店ぐらいです。
![]()
1Fに遊戯設備があり、そのにはC57型の乗り物があります。平和堂は基本的に新幹線と205系が多いのですが、SLなのは米原店ぐらいです。そうそう、米原はSL北びわこ号の起点駅なので、それに習ってSLを置いたのでしょうか・・・。北びわこ号はC56型が基本ですが、たまにC57型も牽引するので、まさにピッタリですね・・・。
東海道本線米原以東には平和堂店舗が無いので(フレンドマートはあるけど・・・)、以上になります。
その2(湖西線・北陸本線編)に続きます。
![]()
![]()
![]()