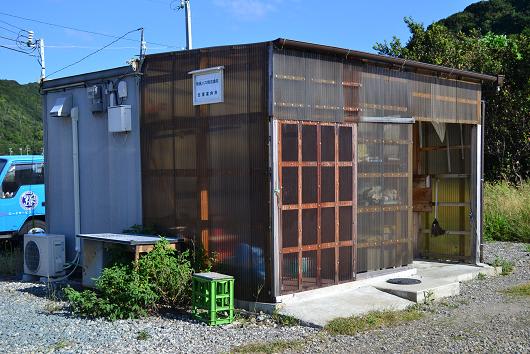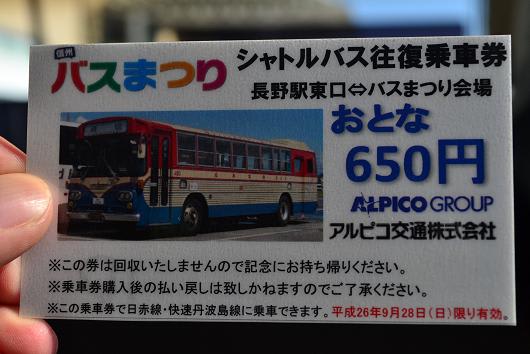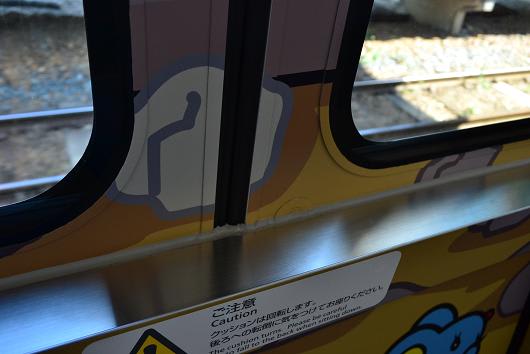西日本JRバスでは2013年に
ノンステ新車
を投入し、園福線で活躍しています。西日本JRバスではKC代投入後、2004年にPA代のワンステが投入されていますが、今回の新車はそれ以来となる一般路線用新車で、ノンステは初めてとなります。
ノンステ新車は2013年秋に3台が入り、2014年3月に更に1台追加されています。
![]()
![]()
こちらは2013年9月に投入された
531−3940
で、エルガのノンステです。大型車の新車はKC代以来となるので、約15年ぶりになるでしょうか・・・。エルガはQPG−LV234N3で、サーモキング製のクーラーが採用されています。そのエルガは郊外仕様で、右側給油です。
JRバスで大型ノンステの新車を入れるのケースは少なく、北海道、中国、九州に次いで4例目となります。西日本JRバスがあそこまでやるとは思いもしませんでした・・・。
![]()
![]()
こちらは2013年9月に投入された
331−3941
で、エルガミオのノンステです。エルガミオの新車は約9年ぶりですが、ノンステは今回が初めてとなります。SKG−LR290J1で、サーモキング製のクーラーが採用されています。エルガと同じく郊外仕様で、右側給油です。
![]()
![]()
こちらは2013年9月に投入された
331−3942
で、エルガミオのノンステです。仕様は331−3941と同じです。
![]()
![]()
こちらは2014年3月に投入された
331−3941
で、エルガミオのノンステです。2013年投入分の増備車にあたるものですが、仕様はほぼ同じのようですね。
これによりノンステが4台になったわけですが、私が撮影した時は3台が動いていて、半分以上がノンステによる運行になっていました。因みに桧山バス停の時刻にはノンステダイヤが書かれていますが、撮影当日はそれ以上にノンステが運行されていました。
![]()
![]()
![]()
![]()
桧山で見かけたツーステたちです。ツーステはエアロミディが2台、エアロスターが2台(うち1台は走行中に目撃)、キュービックが1台の計5台がいるのを確認しています。でも、顔ぶれが京都とほぼ変わらないせいか、減ったような印象がありませんでした・・・。最古参はエアロミディの334−5911でした。
車庫内での撮影は事務室の許可をいただいております。
以上です。
ノンステ新車
を投入し、園福線で活躍しています。西日本JRバスではKC代投入後、2004年にPA代のワンステが投入されていますが、今回の新車はそれ以来となる一般路線用新車で、ノンステは初めてとなります。
ノンステ新車は2013年秋に3台が入り、2014年3月に更に1台追加されています。


こちらは2013年9月に投入された
531−3940
で、エルガのノンステです。大型車の新車はKC代以来となるので、約15年ぶりになるでしょうか・・・。エルガはQPG−LV234N3で、サーモキング製のクーラーが採用されています。そのエルガは郊外仕様で、右側給油です。
JRバスで大型ノンステの新車を入れるのケースは少なく、北海道、中国、九州に次いで4例目となります。西日本JRバスがあそこまでやるとは思いもしませんでした・・・。


こちらは2013年9月に投入された
331−3941
で、エルガミオのノンステです。エルガミオの新車は約9年ぶりですが、ノンステは今回が初めてとなります。SKG−LR290J1で、サーモキング製のクーラーが採用されています。エルガと同じく郊外仕様で、右側給油です。


こちらは2013年9月に投入された
331−3942
で、エルガミオのノンステです。仕様は331−3941と同じです。


こちらは2014年3月に投入された
331−3941
で、エルガミオのノンステです。2013年投入分の増備車にあたるものですが、仕様はほぼ同じのようですね。
これによりノンステが4台になったわけですが、私が撮影した時は3台が動いていて、半分以上がノンステによる運行になっていました。因みに桧山バス停の時刻にはノンステダイヤが書かれていますが、撮影当日はそれ以上にノンステが運行されていました。




桧山で見かけたツーステたちです。ツーステはエアロミディが2台、エアロスターが2台(うち1台は走行中に目撃)、キュービックが1台の計5台がいるのを確認しています。でも、顔ぶれが京都とほぼ変わらないせいか、減ったような印象がありませんでした・・・。最古参はエアロミディの334−5911でした。
車庫内での撮影は事務室の許可をいただいております。
以上です。