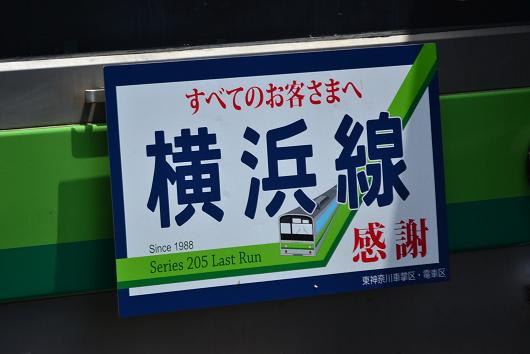7月21日に中央本線・篠ノ井線の茅野〜長野間において
快速「懐かしの115系湘南色」
が運行されました。この列車には115系湘南色3両編成にクモヤ143形を連結した編成で運行されました。そういうわけで、その列車に乗車&撮影してきましたので、レポートします。
![]()
長野方先頭の
クモヤ143−52
です。クモヤ143形50番台は元々クモニ143形で、1978年に製造されました。荷物輸送の廃止により、牽引車へ転用され、この時にクモヤ143形に改番されています。今回充当された52は松本車両センターに所属し、霜取り列車などで活躍しているようです。
![]()
![]()
![]()
115系は長野車両センター所属の
N9編成
が充当されていました。N9編成は信州色でしたが、今年の3月に湘南色に塗り替えられています。N9編成は長野では一般的なオール1000番台の編成です。茅野方先頭車のクモハ115−1079には専用のHMが装着されていました。
![]()
クモヤ143形と115系の連結部です。昔はこういう連結シーンが多く見られましたが、今は貴重になってしまったんですね・・・。
![]()
![]()
![]()
N9編成です。長野方から
クハ115−1227
モハ114−1185
クモハ115−1079
です。長野地区生え抜きの車両たちで揃えられています。この編成は未リニューアルなので、車内はほぼ原形をとどめている事がポイントです。
![]()
![]()
7月21日の早朝に運行された送り込み回送を上諏訪で撮影しました。早朝に松本を出て富士見まで行った後、折返し茅野まで回送されています。確か、上諏訪で少々停車するはずだったような気がするのですが、そのまま通過していました。
![]()
![]()
快速「懐かしの115系湘南色」は7時51分に茅野の1番ホームに入線し、8時6分定刻に出発しました。この列車は3両編成であるがゆえに座席はほぼ埋まり、立ち客が出るほどの混雑でした。横須賀色の時は6両編成そして2日間だったということもあり、空いていたような印象でした・・・。
![]()
列車は上諏訪、下諏訪、岡谷と停車し、岡谷からは旧線を経由しました。普段はE127系が往復するだけの静かな路線ですが、この時だけは凄いにぎわいでした。旧線では辰野と小野に停車し、塩尻に到着しました。ここから篠ノ井線に入り、松本や姨捨などに停車しています。各駅で数分程度停車していたので、のんびりな感じでした。
![]()
![]()
列車は
桑ノ原信号場
に停車し、ここで後続のE127系普通列車に抜かされました。篠ノ井線には急勾配のために姨捨駅と桑ノ原信号場や羽尾信号場といったスイッチバックが設けられていましたが、羽尾信号場が廃止されたため、篠ノ井線では唯一のスイッチバック式の信号場となっています。確か、ここに停車する定期旅客列車は無かったはずなので、貴重なシーンでしょうか・・・。列車はここで約20分間停車していました(後続列車に抜かされただけでなく、上り列車との交換もありました)。因みにE127系の普通列車は通常の乗客だけでなく、沿線での撮影者の移動・回収列車にもなっていたため、大混雑状態でした・・・。
![]()
11時24分定刻に終点の長野に到着しました。信越本線直江津方面の列車が発着している2番ホームに到着し、ここで降車扱いを行い、篠ノ井方面の留置線で折り返し待ちしていました。
以上です。
快速「懐かしの115系湘南色」
が運行されました。この列車には115系湘南色3両編成にクモヤ143形を連結した編成で運行されました。そういうわけで、その列車に乗車&撮影してきましたので、レポートします。

長野方先頭の
クモヤ143−52
です。クモヤ143形50番台は元々クモニ143形で、1978年に製造されました。荷物輸送の廃止により、牽引車へ転用され、この時にクモヤ143形に改番されています。今回充当された52は松本車両センターに所属し、霜取り列車などで活躍しているようです。



115系は長野車両センター所属の
N9編成
が充当されていました。N9編成は信州色でしたが、今年の3月に湘南色に塗り替えられています。N9編成は長野では一般的なオール1000番台の編成です。茅野方先頭車のクモハ115−1079には専用のHMが装着されていました。

クモヤ143形と115系の連結部です。昔はこういう連結シーンが多く見られましたが、今は貴重になってしまったんですね・・・。



N9編成です。長野方から
クハ115−1227
モハ114−1185
クモハ115−1079
です。長野地区生え抜きの車両たちで揃えられています。この編成は未リニューアルなので、車内はほぼ原形をとどめている事がポイントです。


7月21日の早朝に運行された送り込み回送を上諏訪で撮影しました。早朝に松本を出て富士見まで行った後、折返し茅野まで回送されています。確か、上諏訪で少々停車するはずだったような気がするのですが、そのまま通過していました。


快速「懐かしの115系湘南色」は7時51分に茅野の1番ホームに入線し、8時6分定刻に出発しました。この列車は3両編成であるがゆえに座席はほぼ埋まり、立ち客が出るほどの混雑でした。横須賀色の時は6両編成そして2日間だったということもあり、空いていたような印象でした・・・。

列車は上諏訪、下諏訪、岡谷と停車し、岡谷からは旧線を経由しました。普段はE127系が往復するだけの静かな路線ですが、この時だけは凄いにぎわいでした。旧線では辰野と小野に停車し、塩尻に到着しました。ここから篠ノ井線に入り、松本や姨捨などに停車しています。各駅で数分程度停車していたので、のんびりな感じでした。


列車は
桑ノ原信号場
に停車し、ここで後続のE127系普通列車に抜かされました。篠ノ井線には急勾配のために姨捨駅と桑ノ原信号場や羽尾信号場といったスイッチバックが設けられていましたが、羽尾信号場が廃止されたため、篠ノ井線では唯一のスイッチバック式の信号場となっています。確か、ここに停車する定期旅客列車は無かったはずなので、貴重なシーンでしょうか・・・。列車はここで約20分間停車していました(後続列車に抜かされただけでなく、上り列車との交換もありました)。因みにE127系の普通列車は通常の乗客だけでなく、沿線での撮影者の移動・回収列車にもなっていたため、大混雑状態でした・・・。

11時24分定刻に終点の長野に到着しました。信越本線直江津方面の列車が発着している2番ホームに到着し、ここで降車扱いを行い、篠ノ井方面の留置線で折り返し待ちしていました。
以上です。