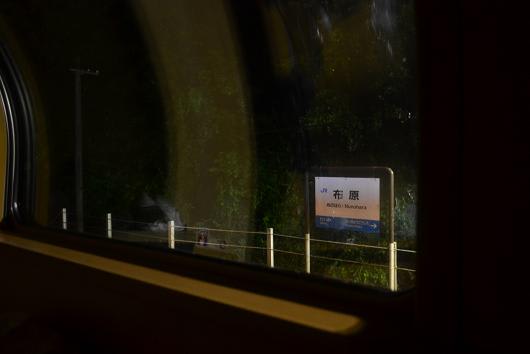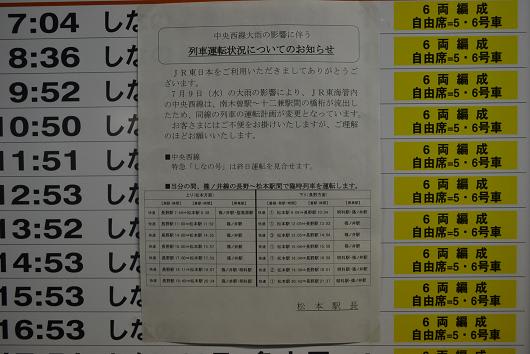福島交通について、船引、石川、塙での様子をレポートしましたが、ここでは福島と郡山での見たままをレポートします。ここ1年間で新車の投入や中古車の投入があり、少しずつ顔ぶれが変わってきています。
![]()
![]()
![]()
2014年に入って
エアロミディノンステ
の新車が5台投入されました。エアロミディは2013年末に福島と白河に各1台ずつが投入されましたが、今回は福島に2台入っただけでなく石川にも2台が投入され、いわきナンバーのTKG−MKが登場しました。残り1台はどこか不明ですが・・・。
ただ、エルガミオやレインボー?も継続して投入しているようで、3メーカー並行投入している感じでしょうか・・・。
![]()
こちらは
元東急バス
のブルーリボンノンステです。写真は福島所属のものですが、通常は中型車が充当されているももりんバスに充当されていました。撮影は平日の朝ラッシュだったので、平日の朝ラッシュ限定で大型車が入っているような感じでしょうか・・・。
![]()
![]()
![]()
![]()
こちらは
元京王バス
の日野HRの中型ロングです。結構な台数が入っているようで、郡山と福島の両方ともそこそこ見かけました。上から1626(福島)、1638(郡山)、1641(福島)、1657(郡山)です。
![]()
![]()
![]()
元京王バスの日野HRと並行して
元神奈川中央交通
のエアロミディも投入されています。KK−MKのツーステです。運賃支払い表示は埋められましたが、側面の出入口幕はそのまま使われています。福島と郡山の両方で見かけました。
![]()
こちらは平日朝の福島駅東口発の1本のみしか設定されていない
第二日東
行きのバスです。福島駅から荒井・土湯温泉方面の区間便的な感じで、福島西IC付近にある工業試験場の通勤輸送を担っているようです。
![]()
こちらはJRバス東北ですが、2013年に久しぶりに大型車の新車としてエルガのワンステが入ったようです。標準尺です。
以上です。



2014年に入って
エアロミディノンステ
の新車が5台投入されました。エアロミディは2013年末に福島と白河に各1台ずつが投入されましたが、今回は福島に2台入っただけでなく石川にも2台が投入され、いわきナンバーのTKG−MKが登場しました。残り1台はどこか不明ですが・・・。
ただ、エルガミオやレインボー?も継続して投入しているようで、3メーカー並行投入している感じでしょうか・・・。

こちらは
元東急バス
のブルーリボンノンステです。写真は福島所属のものですが、通常は中型車が充当されているももりんバスに充当されていました。撮影は平日の朝ラッシュだったので、平日の朝ラッシュ限定で大型車が入っているような感じでしょうか・・・。




こちらは
元京王バス
の日野HRの中型ロングです。結構な台数が入っているようで、郡山と福島の両方ともそこそこ見かけました。上から1626(福島)、1638(郡山)、1641(福島)、1657(郡山)です。



元京王バスの日野HRと並行して
元神奈川中央交通
のエアロミディも投入されています。KK−MKのツーステです。運賃支払い表示は埋められましたが、側面の出入口幕はそのまま使われています。福島と郡山の両方で見かけました。

こちらは平日朝の福島駅東口発の1本のみしか設定されていない
第二日東
行きのバスです。福島駅から荒井・土湯温泉方面の区間便的な感じで、福島西IC付近にある工業試験場の通勤輸送を担っているようです。

こちらはJRバス東北ですが、2013年に久しぶりに大型車の新車としてエルガのワンステが入ったようです。標準尺です。
以上です。